この物語はシリーズでお届けしています。
▶ Chapter 1:出会い から読む
不倫という複雑な感情の渦の中で起きた出来事を、実体験の言葉で綴る連載です。 心が動いた瞬間、引き返せなくなる前のわずかな予感
その“始まり”を記録します。
あの日、私はただ、仕事の一環として彼に会っただけだった。
特別な感情なんて、ひとつもなかった。
そう、最初は・・・
誕生日の夜

「始めまして、こんにちは。」
そう言って、私はいつも通りの笑顔を浮かべた。
ここは、都会の喧騒から少し奥まった場所にある、大人のための秘密の園
私にとって、それは「職場」であり、私を「奈緒」という名の風俗嬢として生かす場所だった。
今日もまた、ドアの向こうから新しい「お客様」が、それぞれの欲望や寂しさを抱えてやってくる。
私は、この仕事に慣れきっていた。
無数の顔、無数の声、無数の体。
彼らは私にとって、数いる「お客様」の一人であり、その日その時を共有するだけの存在だった。
深い感情を抱くこともなく、ただ与えられた役割を全うする。
それが、この場所で生き抜く術だった。
感情の介入は、混乱しか生まない。
そう、自分に言い聞かせ続けていた。
その日、彼がその部屋のドアを開けるまでは
彼が初めて私の部屋に入ってきた時、正直、特別な印象はなかった。
背は高く、清潔感のある作業着を着ていたけれど、決して目を引くような美男子というわけでもない。
どちらかといえば、地味で真面目そう。
ただ、その落ち着いた佇まいは、数多のギラギラした欲望を抱えた客たちとは一線を画しているようにも見えた。
「本日は、何をして遊びますか?」
いつものように、私はにこやかに尋ねた。
すると彼は、少し照れたように、しかし真っ直ぐに私を見つめて言った。
「実は昨日、僕の誕生日だったんです。だから、自分へのプレゼントに、ここに、来たんです」
その言葉に、私は少し驚いた。
誕生日を風俗で過ごす男など、珍しくはない。
だが、それをこんなにも正直に、そして少し恥ずかしそうに話す客は初めてだった。
まるで、大切な秘密を打ち明ける子供のような、そんな純粋さがそこにはあった。
胸の奥で、小さいけれど確かなざわめきを感じた。
「まあ、お誕生日ですか! おめでとうございます」
とっさに私はそう返した。
いつもより少しだけ、声が弾んだかもしれない。
それからの時間は、予想もしない展開を迎えた。
服を脱がないまま過ぎた時間

彼は、服を脱ごうとはしなかった。
私の隣に座り、ただ静かに、他愛のない会話を始めた。
「奈緒さんは、普段は何をしてるんですか?」
「休日はどう過ごしていますか?」
そんな、まるでカフェで隣に座った知人と話すような、ごく普通の質問。
私は戸惑いながらも、仕事だと割り切り、適当な答えを返した。
彼もまた、自分のことを少しずつ話し始めた。
会社の事、趣味の事そして、会話の中で、ごく自然に、彼はこう口にした。
「子供がまだ小さくて、自分の誕生日だからと言って嫁が何かするわけでもなくて……」
その言葉を聞いても、私の心は全く動かなかった。
この仕事をしていると、既婚者の客など珍しくもない。
むしろ、その方が圧倒的に多い。
家庭がありながら、秘密の扉を叩きに来る男たち
その現実に、私はとうに慣れきっていた。
だから、「ああ、そうなんですか」と、ただそれだけを返した。
彼の言葉は、私の仕事とは無関係の、単なる情報の一つに過ぎなかった。
その日の彼は、本当にただ会話をするだけで、私に触れることさえしなかった。
時間が終わる頃、彼は礼を言い、深々と頭を下げて部屋を出ていった。
後に残されたのは、彼の服についていた柔軟剤の香りと、ほんの少しの、奇妙な静寂だった。
私はいつものようにシーツを交換し、次の客を待った。
彼のことなど、すぐに忘れてしまうだろうと、その時はそう思っていた。
何度目かの再開

その後も、彼はときどき予約を入れてくれた。
会うたびに、同じように向かい合って話をした。
お互いの仕事や日常、どうでもいいような世間話。
不思議と会話が途切れない。
何度目かの接客のとき、彼はふいに言った。
「……付き合ってくれない?」
驚きで言葉が出なかった。
私と彼は“仕事と客”という関係だと思っていたのに、その枠を越える言葉だった。
私は笑ってごまかした。
「友達ならいいですよ」
そのときは、本気にするつもりなんてなかった。
彼は既婚者。しかも子供がいる。
深く関われば、必ず誰かが傷つく。
そんなこと、誰よりも私が知っていた。
変わっていく距離感

風俗嬢として、私はお客様の欲望を叶えるのが仕事だ。
しかし、彼の欲望は、これまで私が経験してきたどんなお客様とも違っていた。
それは肉体的なものではなく、もっと深く、精神的な、そして恋愛感情に似た、純粋な「繋がり」を求めるものだった。
「だめだ……」
心の声がそう叫んでいるのに。
なぜか、だんだんと、彼が特別な存在になっていった。
最初は数いるお客様の一人だった。
私の仕事は、彼からお金をもらうこと。
そんな関係性の中で、どうして、私の心はこんなにも、彼を求めてしまったのだろう。
彼の隣にいると、ただの「奈緒」でいられた。
飾らない、偽りのない自分を、彼だけに見せられる気がした。
この仕事をするようになってから、ずっと置き去りにしてきた「私」という個人を、彼はそっと見つけ出してくれた。
友達として、という距離を保っているはずなのに、会えば会うほど、その枠はぼやけていった。
そして、始まり
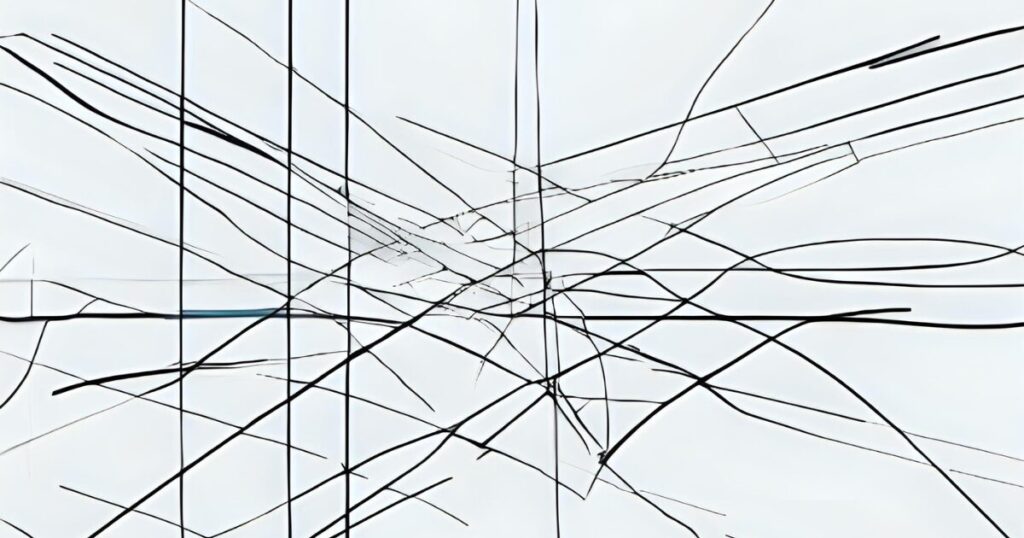
いつからだったのだろう。
彼を“お客様”ではなく、“特別な人”と感じるようになったのは。
風俗嬢という仕事柄、恋愛感情は切り離すのが鉄則だ。
でも、彼との時間だけは、仕事ではなくプライベートのように感じてしまう。
優しい言葉、さりげない仕草、私だけに向けられる視線。
あの日、「友達で」と答えた私の気持ちは、もう変わっていた。
この関係が正しいかどうかなんて、考えなかった。
ただ、彼と会いたい。
話したい。
笑い合いたい。
そう思う気持ちが、日ごとに強くなっていった。
こうして私の“不倫”は、静かに始まった。
次回予告

あの日、ただの「お客様」だったはずの彼。
けれど、ほんの小さな会話の積み重ねが、心の距離を少しずつ近づけていく。
次回「距離が縮まる時間」――禁じられた親密さが始まる。
▶ 次の記事:距離が縮まる瞬間




















